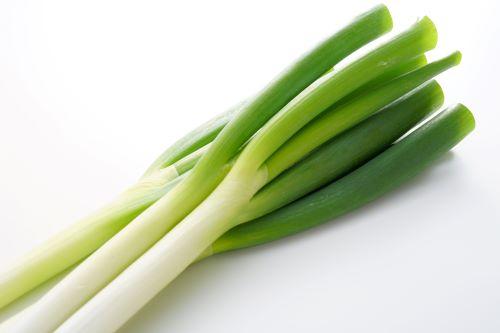今回紹介するのは、エリンギの食べすぎによる身体への影響だ。エリンギのようなきのこ類は人工栽培されており、一年を通して気軽に購入できるのが嬉しいポイント。ヘルシーで身体によい健康効果をもたらしてくれそうな食べ物だが、食べすぎるとどのような影響を及ぼすのだろうか。
目次
- 1. エリンギの食べすぎによる身体への影響
- 2. エリンギの食べすぎにならない量
- 3. エリンギを食べすぎずに適量とるメリット
1. エリンギの食べすぎによる身体への影響

エリンギは鍋に入れたりバター焼きに調理したり、炒めて食べたりといろいろな食べ方で楽しめる食材のひとつだ。えのきだけ・しめじ・しいたけ・まいたけ・なめこのような同じきのこ類の中で、とくに食物繊維を多く含んでいる。食物繊維は体内の余分なコレステロールを排出したり、腸の運動を活発にしたり、便秘解消に効果が期待できるのが特徴だ(※1)。エリンギを食べすぎると、下痢など、消化機能に影響を及ぼすのだろうか。
便秘や下痢
エリンギに含まれる食物繊維は、第6の栄養素と呼ばれるほど人間の身体にとって大切な成分だ。日本人の多くが摂取不足と考えられており、食べすぎるケースはあまりない。しかし過剰摂取すると、便がやわらかくなったり栄養素の吸収率が低下したりする可能性がある。食物繊維は摂取不足と食べすぎに注意して、適量を摂ることが大切だ(※2)。
調理方法によっては太る可能性も
エリンギのカロリーは低いが、調味料や調理法によってカロリー過多になる可能性がある。調理法ごとのカロリーを紹介しよう。
100gあたりのエリンギのカロリー(※3、4、5、6)
生エリンギ:31kcal
茹でエリンギ:32kcal
焼きエリンギ:41kcal
油炒めエリンギ:69kcal
茹でエリンギと油炒めエリンギでは、倍以上カロリーが異なることがわかるだろう。次にエリンギを調理した料理のカロリーを紹介する。
1人前のエリンギ料理のカロリー(※1、7、8)
エリンギと魚介のマリネ:61kcal
エリンギのカレー炒め:85kcal
エリンギとシソの豚肉巻き炒め:113kcal
エリンギごはん:189kcal
調理法によりカロリーが異なることも理解できるだろう。
2. エリンギの食べすぎにならない量

一日に何をどれくらいの量、食べたらいいのかわからないという人もいるだろう。農林水産省の食事バランスガイドを元にエリンギの食べすぎない量を解説する。
一日の摂取量
私たち人間の身体活動レベルは日常生活と運動のような活動量により、3つに分けられる。
身体活動レベル(※9)
低い:一日をほとんど座って過ごす人
ふつう:座って仕事をする時間が多いが、軽い運動または散歩をする人
高い:移動と立ち仕事が多い人か、活発な運動習慣がある人
Advertisements
一日に何をどれくらいの量、食べたらよいのかは食事バランスガイドを見ればわかる。一日に必要なエネルギー量から、主食・副菜・主菜・牛乳と乳製品・果物の5つの料理ごとに、一日にどれだけの量を食べるとよいかの量が決まる。単位は「1つ(SV)主材料の重量約70g」だ。エリンギのようなきのこ類や野菜、海藻は副菜に含まれる。副菜は一日に5~7つ(SV)が目安量だ。そのうち、きのこは50~100gを目安にするとよいだろう(※9、10、13)。
3. エリンギを食べすぎずに適量とるメリット

Advertisements
エリンギを食べすぎずに適量とるメリットを紹介しよう。食物繊維をはじめ、どういった栄養素がエリンギに含まれているのだろうか。その栄養素の働きとは?
ビタミンD
エリンギに含まれる栄養素のひとつが、ビタミンDだ(※3)。野菜や穀物、いも類、豆にほとんど含まれていないビタミンDはカルシウムの吸収を促し、骨を丈夫にして筋力を高める働きがある。骨を丈夫にしようとカルシウムを摂取しても、ビタミンDが不足していると十分に吸収されない。日光にあたると皮膚でビタミンDが作られるが、紫外線量が少ない冬は不足しがちだ。とくに冬はエリンギのようなビタミンDを含む食品を積極的に食べること(※11)。
カリウム
エリンギに含まれるカリウムは細胞内に最も多いミネラルだ(※3、12)。人が生きていくのに大切な成分で、ナトリウムとともにブラザーイオンと呼ばれており、お互いが協力し合って働く。カリウムが不足すると食欲不振・脱水・無関心・筋力低下・不安感・吐き気といった症状が出る可能性がある(※12)。
食物繊維
先述したようにエリンギは食物繊維を豊富に含んでいる(※3)。食物繊維は水溶性食物繊維と不溶性食物繊維がある。とくにエリンギは水溶性食物繊維より、不溶性食物繊維のほうが豊富だ。働きは便をやわらかくするので便秘解消や、腸内で善玉菌を増やす効果が期待できる(※2)。
結論
エリンギを食べすぎると身体にどういう影響を及ぼすのかを紹介した。先述したようにエリンギに含まれる食物繊維は過剰摂取すると、便がやわらかくなったり栄養素の吸収率が低下したりする可能性がある。食べすぎには注意して、適量を食べるのがおすすめだ。
(参考文献)
※1出典:一般社団法人 福山市医師会「該当ページ名:vol.76 エリンギ」
https://www.fmed.jp/cnt/kenkou/recipe/kinokorui/eringi.html
※2出典:サントリーホールディングス株式会社「食物繊維をとりすぎるとどうなる?食物繊維が不足した場合のリスクについても解説」
https://www.suntory-kenko.com/column2/article/6415/
※3〜※6出典:文部科学省
https://fooddb.mext.go.jp/※7※8出典:第一三共株式会社
https://www.ehealthyrecipe.com/
※9※10出典:農林水産省
https://www.maff.go.jp/
※11出典:公益財団法人 骨粗鬆症財団「ビタミンDを多く含む食品」
https://www.jpof.or.jp/Portals/0/images/publication/leaf_02_181003.pdf
※12出典:一般社団法人 オーソモレキュラー栄養医学研究所「カリウム」
https://www.orthomolecular .jp/nutrition/potassium/
※13出典:順天堂東京江東高齢者医療センター 2021年10月発行「栄養だより」
https://hosp-gmc.juntendo.ac.jp/