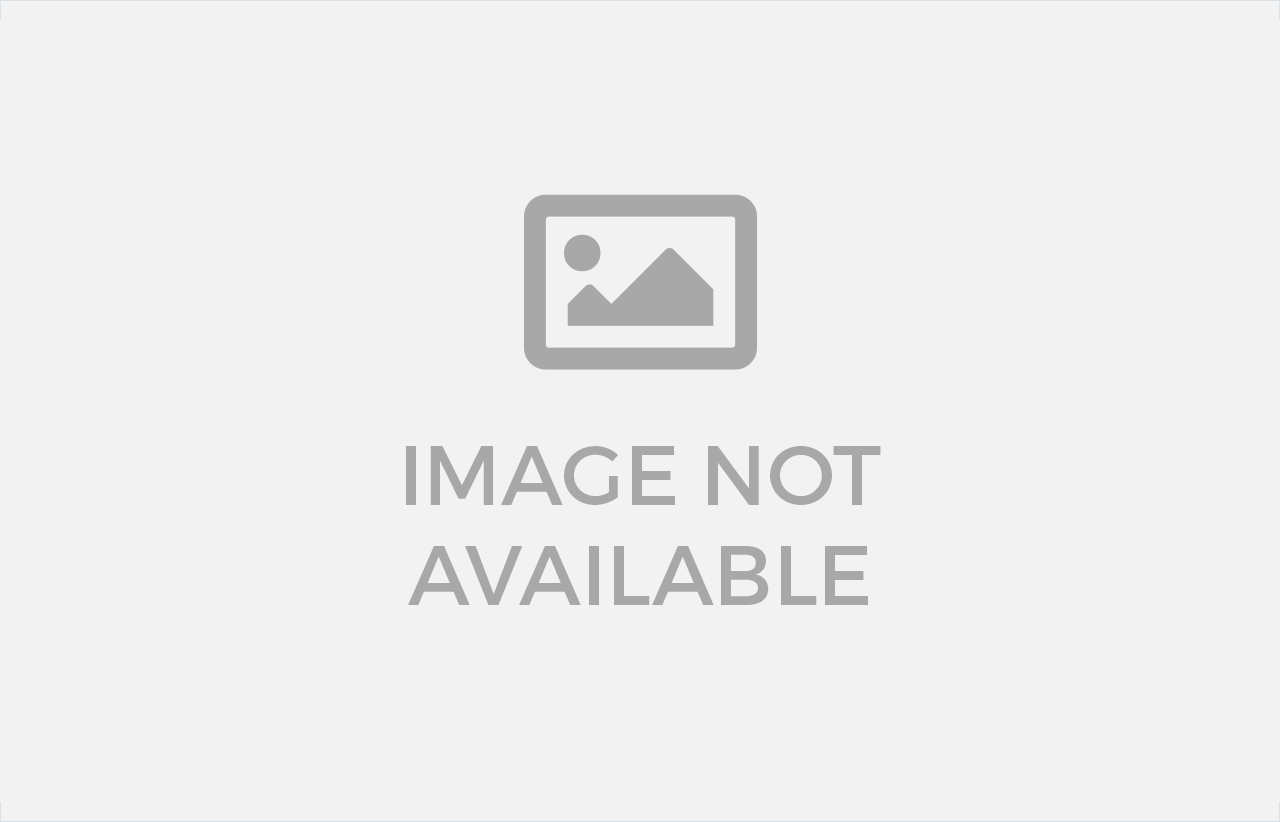監修者:管理栄養士 児玉智絢(こだまちひろ)
低価格で栄養価の高い納豆。納豆を食べる際、何回かき混ぜて食べているだろうか。実は、美味しくなるおすすめの混ぜる回数があるのだ。そこで今回は、納豆を混ぜる回数や混ぜ方、おすすめの食べ方などを紹介していこう。納豆をよく食べる方や納豆を何回混ぜたらよいのかわからない方はぜひ参考にしてほしい。
目次
- 1. 納豆を混ぜる回数
- 2. 納豆を混ぜる回数とコク
- 3. 納豆を混ぜる回数とお茶漬け
1. 納豆を混ぜる回数

納豆を食べるときに話題になりやすい、混ぜる回数。納豆を混ぜる回数はどのくらいがよいのだろうか。納豆が大好きだったという有名な美食家「北大路魯山人」は納豆の混ぜ方について自身の著書で綴っている。以下で詳しく見ていこう。
美食家の混ぜ方
北大路魯山人は、幅広い芸術分野で功績を残している芸術家の1人で、何より美食家として名を馳せた人物だ。この美食家はまず納豆を器に移し、それに何も加えない状態で2本の箸を使いよく混ぜる。何も加えない状態でよく混ぜると納豆の糸がたくさん出て固く練りにくくなってくるが、この糸を出すほど美味しいと魯山人は提唱しているのだ。しっかりと混ぜたら醤油を数滴垂らし、さらに混ぜて醤油を加えてという動作を繰り返す。糸が見えないほどにどろどろになったら、お好みで辛子やネギのみじん切りなどを加えて少し混ぜる。すると味がより強くなり美味しくなるとされているのだ。424回かき混ぜるという説もあるが「何も加えずに糸が出るくらいしっかり混ぜる」ということを推奨している。
2. 納豆を混ぜる回数とコク

では納豆を何回混ぜるのがおすすめなのだろうか。おすすめの納豆を混ぜる回数を以下で紹介していこう。
コクが出る回数
納豆にコクが出る混ぜる回数は424回とされている。混ぜる回数を424回にすると、塩カドが取れてまろやかな味わいに変化するのだ。さらに、納豆を424回混ぜると、コク成分が109%に増えるという結果がある。また、納豆をたくさん混ぜると粘り気が出てくるが、この粘り気の正体は、旨み成分であるグルタミン酸だ。(※1)粘り気が増えれば増えるほど、旨みが強くなる。しかし、旨み成分を増やそうとして400回以上混ぜても、旨み成分は変わらず、かえって納豆の粒が崩れ残念な食感になってしまうため注意が必要だ。
Advertisements
なかなか自分で400回以上納豆を混ぜるのは大変だが、美味しくなるなら試してみる価値はあるだろう。どうしても時間がないときは、全国納豆協同組合連合会の会長が提唱している、110回を目安に混ぜていただくのがおすすめだ。
また、ある有名玩具メーカーは、納豆を424回混ぜられる「魯山人納豆鉢」というマシンを発売している。興味のある方や自力で納豆を混ぜるのが大変な方は試してみるとよいだろう。
3. 納豆を混ぜる回数とお茶漬け

Advertisements
納豆を混ぜる回数についてお伝えしてきた。以下では、納豆のお茶漬けについてやり方やポイント、混ぜる回数などを見ていこう。
やり方とポイント
まず納豆のお茶漬けを作る前に、前述した混ぜる回数424回納豆を混ぜておく。茶碗に温かいごはんを少量盛り、その上によく混ぜた納豆を乗せ、その上から煎茶をかける。塩気が足りない場合は、後から醤油を数滴垂らすのがポイントだ。また、納豆とごはんの割合は、1:4が望ましいと魯山人は提唱している。大葉や生姜、鮭フレーク、白ごま、明太子、チーズなどを乗せて、さまざまなアレンジを楽しむのもおすすめだ。食欲がないときや忙しいときにぜひ試してほしい。
結論
納豆は回数を多く混ぜた方が美味しくなることがわかった。少ない回数ではないため、自分で混ぜるのは大変だが、いつもの納豆をより美味しく食べられるのなら試してみても損はないだろう。普段なんとなく納豆をかき混ぜて食べている方は、ぜひこの記事を参考によく混ぜて食べてみてはいかがだろうか。
(参考文献)
- ※1東北大学病院生理検査センター
- 第36回 納豆でつくる素敵な食生活 | 東北大学病院生理検査センターホームページhttp://www.physiology.hosp.tohoku.ac.jp/custom65.html